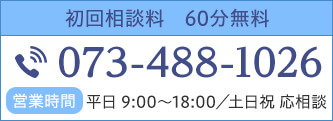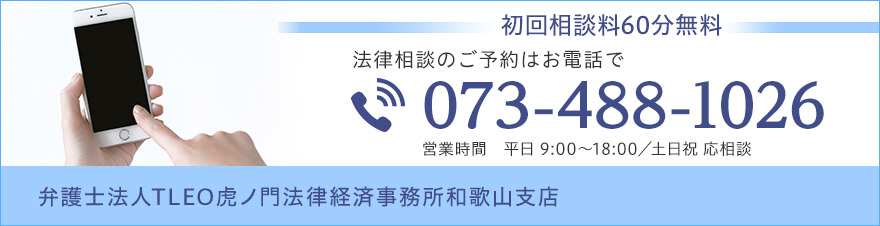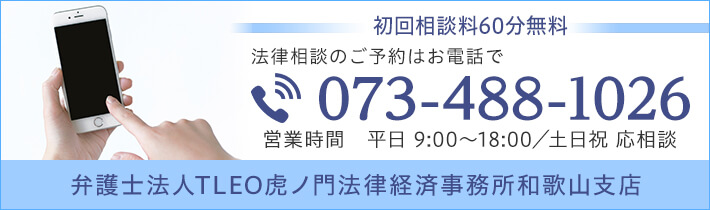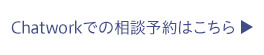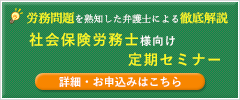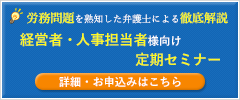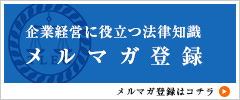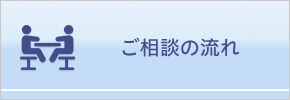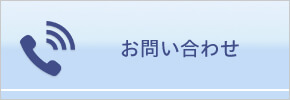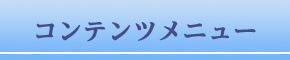残業代請求されないための雇用契約チェック【管理監督者性の判断基準】
文責:弁護士 野上 晶平
目次
- 管理監督者とは
- 残業代問題
- 判断基準
- 管理監督者と認められなかった判例
- 日本マクドナルド事件
- 九九プラス事件
- ほるぷ事件
- 播州信用金庫事件
- 岡部製作所事件
- セントラル・パーク事件
- レストラン「ビュッフェ」事件
- バズ(美容室副店長)事件
- 育英舎事件
- 風月荘事件 - 管理監督者と認められた判例
- 徳洲会事件
- 日本ファースト証券事件
- 姪浜タクシー事件 - まとめ
管理監督者とは
管理監督者とは、労働基準法第41条第2項にある『監督若しくは管理の地位にある者』のことで、管理監督者に該当する労働者は、労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されません。
つまり、管理監督者が法定労働時間(原則:週40時間、1日8時間)を超えて働いたり、法定休日(週1回または、4週間を通じて4日)に働いたとしても残業代は発生しないのです。
また、管理監督者と似たものとして、働き方改革法で新たに創設された「高度プロフェッショナル制度」がありますが、こちらについては、コラム【働き方改革法の成立で何が変わる?】でご紹介しています。
【主な「管理監督者」と「高度プロフェッショナル制度」の違い】
| 管理監督者 | 高度プロフェッショナル制度 | |
| 労働者の同意 | 同意の有無にかかわらず、 要件に該当しているかで判断 |
必要 |
| 職種 | 指定なし | 厚生労働省令で定める業務 |
| 深夜の割増賃金 | 支払う必要あり | 支払う必要なし |
※ 注意 ※
どちらも、年次有給休暇についての規定は適用されるので、2019年4月から義務付けられた『年5日の年次有給休暇の確実な取得』をさせなければなりません。(休日≠休暇です。)
残業代問題
この規定を誤って解釈してしまい、経費を削減するために、管理監督者としての要件を満たしていないにも関わらず管理監督者として扱い残業代を払わないでいる(いわゆる『名ばかり管理職』として扱っている)と、突然、労働者から残業代を
請求されることがあります。
そして、裁判などで、その労働者が管理監督者なかったと判断されると(多額の)残業代を支払わなければならないのです。
このように「本来、受け取ることができる残業代を受け取っていなかった労働者」が残業代請求をしてくるというものが【残業代問題】の1つとなっています。
この問題を防ぐためには、事前に管理監督者に該当するのかの雇用契約のチェックを弁護士などの専門家に確認してもらうことが大切です。
判断基準
次の3項目が、管理監督者に該当するのかの判断基準となります。
①経営者との一体性
②出退勤・労働時間の自由裁量(※1)
③給与を中心とする処遇・待遇
では実際に、過去の判例を判断基準と合わせて確認していきましょう。
※1
2019年4月から、事業者は管理監督者についても労働時間を把握しなければならないことになりました。
【労働安全衛生法第66条の8の3】
事業者は、(中略)面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、
労働者(次条第一項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない。
【労働安全衛生法第2条第2項】
労働者
労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は
事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
【労働基準法第9条】
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所
(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
【労働案税衛生法第66条の8の3】にある「次条第一項に規定する者」とは高度プロフェッショナル制度の労働者のことで、他の労働者とは別に医師による
面接指導の条件について規定されています
(健康管理時間が、労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超えるものに対し、。
厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。)
管理監督者と認められなかった判例
日本マクドナルド事件(平成20年1月28日 東京地方裁判所)
①経営者との一体性
- アルバイト従業員の採用・育成
- 従業員の勤務シフトの決定
- 販売促進活動の企画、実施等に関する権限
など店舗運営において重要な職責を負っているが、職務・権限は店舗内の事項に限られている。
②出退勤・労働時間の自由裁量
【形式的な労働時間裁量】
- 自らのスケジュールを決定する権限
- 早退や遅刻に関して、上司の許可を得る必要はない
【勤務実態からみる労働時間裁量】
- 店長として固有の業務を遂行する時間(150時間程度)を要する
- 勤務態勢上の必要性から、自らシフトマネージャーとして勤務し、
長時間の時間外労働を余儀なくされている
③給与を中心とする処遇・待遇
【管理監督者として扱われている店長の年額賃金】
S評価:約780万円
A評価:約700万円
B評価:約635万円
C評価:約580万円
【管理監督者として扱われていないファーストアシスタントマネージャーの年額賃金】
約590万円(時間外割増賃金を含む)
店長の
・10%がC評価 ⇒ 下位職種のファーストアシスタントマネージャーより低賃金
・40%がB評価 ⇒下位職種のファーストアシスタントマネージャーとの差額が45万円程度
【判決文】(一部)
経営者との一体的な立場において、労働基準法の労働時間等の枠を超えて事業活動することを
要請されてもやむを得ないものといえような重要な職務と権限を付与されているとは認められない。
(中略)
勤務実態からすると、労働時間に関する自由裁量性があったとは認められない。
(中略)
賃金は、労働基準法の労働時間等の規定の適用を排除される管理監督者に対する
待遇としては、十分であるといい難い。
(全文は裁判所のホームページよりご覧いただけます。)
九九プラス事件(平成23年5月31日 東京地方裁判所立川支部)
①経営者との一体性
- パート・アルバイトを採用することができたが、時給額の裁量、解雇権限は無かった
- 社員の新規採用の決裁権限は無かった
- 経営方針、経営戦略等が伝達されるのみで、店長からの意見聴取や経営方針について
討論する機会はほとんどなかった - 店長とパート・アルバイトとの間で、作業内容が大きく違うということはなかった
- 店長は、700店舗もある直営店の内、1店舗の運営を任されているにすぎない
②出退勤・労働時間の自由裁量
- シフトに穴が空いた場合にはなるべく店長が勤務するといった勤務態様がうかがわれる
- パート・アルバイトと同じ方法により出退勤時刻等が管理されていた
③給与を中心とする処遇・待遇
【超過勤務手当等を考慮して具体的に支給された金額】
店長となる直前の月・・・31万2534円
店長となった月・・・・・26万8390円
店長昇格後の賃金額が、店長昇格前の賃金額より少ない。
(全文は裁判所のホームページよりご覧いただけます。)
ほるぷ事件(平成9年8月1日 東京地方裁判所)
①経営者との一体性
支店営業方針を決定する権限や、具体的な支店の販売計画等に関して独自に指揮命令を行う権限をもっていたとは認められない。
②出退勤・労働時間の自由裁量
タイムカードにより厳格な勤怠管理を受けており、自己の勤務時間について自由裁量を有していなかった。
③給与を中心とする処遇・待遇
営業所販売課長から営業所長になったときに、資格給が5,000円しか増加していない。
(全文は裁判所のホームページよりご覧いただけます。)
播州信用金庫事件(平成20年2月8日 神戸地方裁判所姫路支部)
①経営者との一体性
職員に関する人事評価について、支店長に対して意見できたが、書面として残るものではないので、その重要性は高いとはいえない。参加していた経営者会議も懇親会という色彩が強く、支店長不在時に参加した支店長会議も各支店の報告会というものだった。
②出退勤・労働時間の自由裁量
金庫の開閉という仕事があるため、出勤時刻や退勤時刻を自由に決めることができなかった。
業務内容などから、自由にいわゆる中抜けということができない。
③給与を中心とする処遇・待遇
(判決理由が公益社団法人 全国労働基準関係団体連合会のホームページにて公開されています。)
岡部製作所事件(平成18年5月26日 東京地方裁判所)
①経営者との一体性
知識、経験及び人脈等を動員して一人でやり繰りする専門職的業務で、人事労務の決定権を有していなかった。
②出退勤・労働時間の自由裁量
一般の従業員に近い勤務をしており、自由に決定できなかった。
③給与を中心とする処遇・待遇
(判決理由が公益社団法人 全国労働基準関係団体連合会のホームページにて公開されています。)
セントラル・パーク事件(平成19年3月27日 岡山地方裁判所)
①経営者との一体性
採用や解雇についての最終決定権限はなかった。
②出退勤・労働時間の自由裁量
シフト表を作成していたが、自由に出退勤時間を決めたり、優先して休日をとったりすることは実際には困難だった。
タイムカードの廃止は、他の従業員についても同様の扱いだったため、勤務時間を客観的に把握する状況になかったからといって、出退勤に厳格な規制がなかったとはいえない。
(判決理由が公益社団法人 全国労働基準関係団体連合会のホームページにて公開されています。)
レストラン「ビュッフェ」事件(昭和61年7月30日 大阪地方裁判所)
①経営者との一体性
ウエイターの採用については任されていたが、賃金等の労働条件は、最終的に事業主が決定していた。
②出退勤・労働時間の自由裁量
店舗の営業時間である午前11時から午後10時までは完全に拘束されていて、
タイムレコーダーにより出退勤の時間を管理されていた。
③給与を中心とする処遇・待遇
(判決理由が公益社団法人 全国労働基準関係団体連合会のホームページにて公開されています。)
バズ(美容室副店長)事件(平成20年4月22日 東京地方裁判所)
①経営者との一体性
経営、人事、労務管理等へ関与は限定的であった。
②出退勤・労働時間の自由裁量
自らの業務内容について、その内容及び時間を決定する上で裁量があったが、出退勤管理を受けていた。
③給与を中心とする処遇・待遇
(判決理由が公益社団法人 全国労働基準関係団体連合会のホームページにて公開されています。)
育英舎事件(平成16年4月18日 札幌地方裁判所)
①経営者との一体性
人事管理を含む運営に関する管理業務全般の事務を担当していたが、裁量的な権限は認められておらず、急場の穴埋のような臨時の異動を除いては何の決定権限も有していなかった。
②出退勤・労働時間の自由裁量
どのように管理業務を行うかについての裁量があるだけで、出退勤についてはタイムカードへの記録が求められていて、勤怠管理自体は他の従業員と同様に行われていた。
③給与を中心とする処遇・待遇
課長に昇進してからは、それまでの手当よりも月1万2000円ほど上がり、賞与も多少増額となり、接待費及び交通費として年間30万円の支出が認められ、また、1度だけとはいえ、課長報奨金として70万円が支給されるなど、給与面等での待遇が上がっているが、同程度の給与を受け取っている一般従業員もいることから、その役職にふさわしいものであるともいえない。
(判決理由が公益社団法人 全国労働基準関係団体連合会のホームページにて公開されています。)
風月荘事件(平成13年3月26日 大阪地方裁判所)
①経営者との一体性
営業方針や重要事項の決定に参画する権限が認められていたわけではない。
店舗の人事権も有していなかった。
②出退勤・労働時間の自由裁量
タイムカードの打刻や日間面着表の提出が義務づけられ、日常の就労状況も査定対象とされていた。
③給与を中心とする処遇・待遇
店舗の他の従業員の賃金等に比べ、風紀手当が格段に高額に設定されていた。
(判決理由が公益社団法人 全国労働基準関係団体連合会のホームページにて公開されています。)
管理監督者と認められた判例
徳洲会事件(昭和62年3月31日 大阪地方裁判所)
①経営者との一体性
看護婦の採否の決定、配置等労務管理について経営者と一体的な立場にあった。
②出退勤・労働時間の自由裁量
タイムカードに刻時すべき義務を負っているものの、拘束時間の長さを示すだけにとどまり、
実際の労働時間は自由裁量に任せられ、労働時間については必ずしも厳格な制限を受けていなかった。
③給与を中心とする処遇・待遇
労働時間に応じた時間外手当等が支給されない代わりに、責任手当、特別調整手当が支給されていた。
(判決理由が公益社団法人 全国労働基準関係団体連合会のホームページにて公開されています。)
日本ファースト証券事件(平成20年2月8日 大阪地方裁判所)
①経営者との一体性
- 30名以上の部下を統括する地位にあり、事業経営上重要な上位の職責にあった
- 支店の経営方針を定め、部下を指導監督する権限を有していた
- 中途採用者については実質的に採否を決する権限が与えられていた
- 人事考課を行い、係長以下の人事については自身の裁量で決することができた
- 社員の降格や昇格についても相当な影響力を有していた
②出退勤・労働時間の自由裁量
部下の労務管理を行う一方、自身の出欠勤の有無や労働時間は報告や管理の対象外だった。
③給与を中心とする処遇・待遇
月82万円の賃金(職責手当25万円を含む)を受けており、支店長以下の給与より格段に高かった。
(判決理由が公益社団法人 全国労働基準関係団体連合会のホームページにて公開されています。)
姪浜タクシー事件(平成19年4月26日 福岡地方裁判所)
①経営者との一体性
- 営業部次長として、多数の乗務員を直接に指導・監督する立場にあった
- 乗務員の採否についても、営業部次長の段階における履歴書の審査や面接で不採用とすることがあり、
営業次長の唯一の上司というべき専務の面接に進んだ者で不採用になった者がいなかった
(営業部次長の判断が乗務員の採否に重要な役割を果たしていた) - 取締役や主要な従業員の出席する経営協議会のメンバーだった
- 専務に代わり、会社の代表として会議等へ出席していた
②出退勤・労働時間の自由裁量
出退勤時間についても、多忙なために自由になる時間は少なかったが、専務から何らの指示を受けておらず、会社への連絡だけで出先から帰宅することができる状況にあった。
③給与を中心とする処遇・待遇
基本給及び役務給を含めて700万円余の高額の報酬を得ており、従業員の中で最高額であった。
※ 補足 ※
(判決理由が公益社団法人 全国労働基準関係団体連合会のホームページにて公開されています。)
まとめ
ご紹介した判例から、どのような場合に管理監督者性の判断についてある程度、ご理解いただけたのではないでしょうか。
すべての管理監督者性についての判例をご紹介したわけではありませんが、管理監督者として「認められない」とした判例の方が多くなっています。
これについては、やはり、雇用契約のリーガルチェックができていない企業が多いことが要因の一つになっているのではないでしょうか。
働き方改革が注目されている昨今、労働事件が発生する前に雇用契約や就業規則の見直しをしておくことが大切です。
当事務所では初回相談料を無料とさせていただいていますので、まずはお気軽にご相談ください。