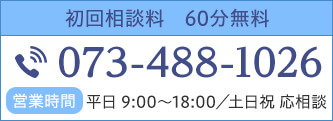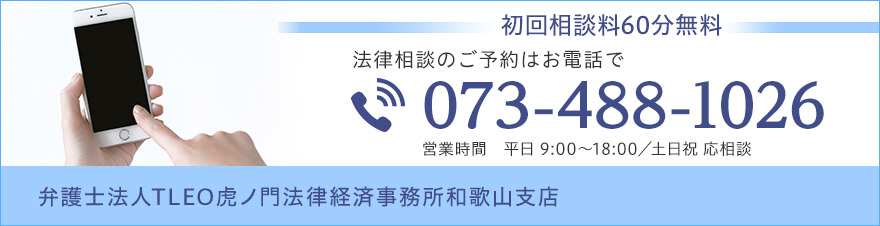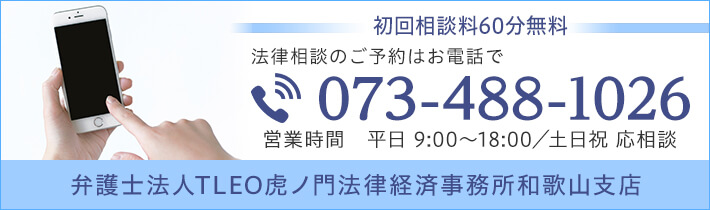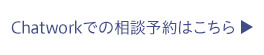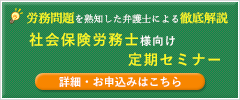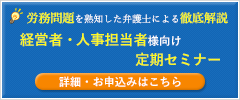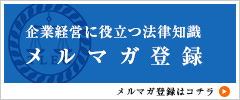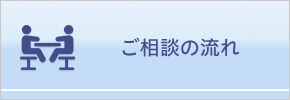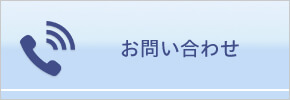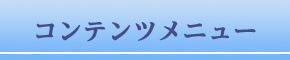解雇
企業が抱える解雇問題への対処方法
- 解雇した従業員から「不当解雇」と言われて困っている
- 問題のある社員を辞めさせたいけれども、手順がわからない
- 就業規則で、懲戒解雇の規定を整備したい
- リストラ(整理解雇)したいが、法律敵意問題のないようにしたい
このようなお悩みを抱えた企業様、弁護士がお力になります!
1.解雇の難しさ
日本の労働法制下において、会社が従業員を解雇することが非常に困難になっています。普通解雇の場合、「解雇権濫用の法理」という法則が適用されるため、解雇が認められる場合が非常に限られてくるからです。
実際には、解雇の合理性と、解雇方法の相当性が認められなければ、解雇は無効になります。単純に「他の従業員よりも能力が劣っている」というだけでは、解雇は認められません。
解雇したいときには、逆説的ですが、まずは解雇を避ける方法を検討しなければなりません。
どのような努力をしても解雇を避けることができない場合に、ようやく解雇が有効となるからです。
綿密な準備なしに従業員に解雇通知を送ったら、「不当解雇」を主張されて、労働基準監督署に通報されたり、労働審判や労働訴訟を起こされたりするリスクを負うこととなります。
2.解雇の種類
解雇には、大きく分けて、①普通解雇、②懲戒解雇、③整理解雇があります。その他、労働契約を終了させるものとしては、当然退職、辞職、合意退職がありますが、前者の解雇は、これらとは異なり、使用者側の一方的な意思表示によって、労働契約を終了させるものとして、後者と区別されます。
①普通解雇について
民法では、期間の定めのない雇用契約について、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる」と規定しています(同法627条1項前段)。これだけ見ると、民法上は、雇用契約の解消は自由であるのが原則となっています。
ところが、判例によって、「使用者の解雇権の行為もそれが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当なものとして是認することができない場合には、権利の濫用として無効になる」(最判昭50・4・25=日本食塩製造事件)とするいわゆる解雇権濫用法理が確立され、、この判例による解雇権濫用法理を条文化したものとして、労契法16条(旧労働基準法18条の2)が規定されたのです。
このように、解雇の合理性と解雇方法の相当性が必要となります。
たとえば、勤務成績・勤務態度不良の従業員や能力不足の従業員を解雇しようとする場面を想定すると、①当該企業の種類、②労働者の職務内容、③労働者の採用理由(職務に要求される能力、勤務態度はどの程度か)、④労働者の勤務成績・勤務態度の不良の程度・回数(企業の業務遂行に支障を生じ、解雇しなければならないほどに高いか。1回の過誤か、繰り返すものか)、⑤労働者の改善の余地の有無、⑥会社の指導の有無(注意・警告をしたり、反省の機会を与えたか)、⑦他の労働者との取扱いの均衡等を総合的に検討するとされています(山口幸雄ほか「労働事件審理ノート〔第3版〕」判例タイムズ社)。
よって、まずは、その従業員に教育・指導・注意をして、スキルを高めるための研修を行ったり、配置転換や降格、減給をするなど、解雇以外の方法を検討する姿勢が求められます。
②懲戒解雇について
懲戒処分は企業秩序違反に対する特別の制裁罰です。懲戒処分のうち最も重い極刑であるとされることから、有効性が争われた場合、とくに厳しく判断される傾向にあります。懲戒解雇事由該当性の判断、相当性も厳しくチェックされます。そのため、懲戒解雇の選択は慎重を期すべきです。
③整理解雇について
整理解雇とは、いわゆる人員整理のための解雇であり、①人員削減の必要性、②解雇回避努力、③人選の合理性、④解雇手続きの相当性という4要素を総合的に考慮して判断することが定着しています。なお、ここで注意していただきたいのは、上記の①~④は、4要件ではなく、4要素であることから、①~④の要素全てを満たす必要はなく、これらの要素に関する諸事情の総合的な判断によることになります。
3.解雇の手順
問題のある従業員をやめさせたい場合には、まずはその従業員に教育・指導・注意をして、スキルを高めるための研修などを行う必要があります。
これらの経過については、書面を作成し、資料化して置きましょう。配置転換や降格、減給などによって対応できるなら、それらの方法で対応すべきです。
どうしても解雇を避けられないなら、まずは「退職勧奨」を行いましょう。退職勧奨をするときには、「強制」と言われないように、公正な方法で行う必要があります。従業員を説得するときには、2名以上で臨み、その様子を録音しておくことをお勧めします。
退職勧奨をしてもどうしても辞めない場合に、ようやく解雇通知を送ることとなります。このとき、きちんと解雇予告手当を支給することも忘れないようにしましょう。
これだけのステップをきっちり踏んでいたら、たとえ裁判を起こされても、企業側が勝てる可能性が相当高くなります。
4.弁護士がお手伝いできること
企業が解雇問題で労働者とトラブルになったら、できるだけ企業の本業である営業活動に支障を与えないことが大切です。
弁護士がご依頼をお受けしたら、企業の代わりに労働者との交渉や労働審判、労働訴訟に臨みますので、企業は対応に追われることはありません。
また、当初から最も適切な対応をとっておくことにより、早期に解決することができますし、たとえ労働訴訟等になっても有利に運ぶことができます。
常日頃から弁護士にご相談ただいていたら、そもそも解雇トラブルの発生を防ぐことができます。
解雇問題でお悩みの場合には、是非ともお気軽にご相談ください。
当事務所のサポートプラン
当事務所が解雇に関するサポートをさせていただく際には顧問プランのご契約をお勧めしております。
| 顧問料(税込) | 月額3.3万円 | 月額5.5万円 | 月額11万円 | 月額16.5万円 |
|---|---|---|---|---|
| プランの選び方 | 法務や税務の知識のある 相談役がほしい |
契約書等のチェックが多い |
||
| ■労務支援コンサルティング | ||||
| 問題社員対応 レクチャー |
||||
| 就業規則の作成・ 見直し |
||||
| ■解雇処分サポート |
||||
相談と助言 |
||||
書面の作成 |
||||
管理・指導 |
||||
| ■ご相談方法・稼働時間 |
||||
| 弁護士稼働時間の目安 | ||||
| 電話での相談 | ||||
| メールでの相談 | ||||
| Chatwork等での相談 | ||||
| 事務所での相談 | ||||
| 訪問での相談 | ||||
| 相談予約の優先対応 | ||||
| 社員やご親族の方 からの相談 |
||||
| ■契約書・利用規約 | ||||
| 契約書の 作成・チェック |
||||
| ■労働問題 | ||||
| 社員との交渉の バックアップ |
||||
| 労働審判・訴訟 | 20%程度割引(※1) |
30%程度割引(※1) |
報酬金30%程度割引(※1) |
報酬金半額(※1) |
| ■債権回収 | ||||
| 支払交渉 | *報酬金はご相談・顧問割引あり |
*報酬金はご相談・顧問割引あり |
||
| 内容証明郵便の発送 (実費のみ別途請求) |
(月1通以下・弁護士名) |
(月1通程度・弁護士名) |
(月3通程度・弁護士名) |
(月5通程度・弁護士名) |
| 訴訟 | 20%程度割引(※1) |
30%程度割引(※1) |
報酬金30%程度割引(※1) |
報酬金半額(※1) |
| ■その他のサービス | ||||
| 顧問弁護士の表示 | ||||
| クレーマー対応 (アドバイス) |
||||
| クレーマー対応 (対応窓口) |
||||
| 上記以外の弁護士費用 | 20%程度割引(※1) |
30%程度割引(※1) |
報酬金30%程度割引(※1) |
報酬金半額(※1) |
| 他の専門家紹介 | ||||
| セミナー無料案内 | ||||
| 社内講師 | ||||
| 趣味その他おつきあい | ||||