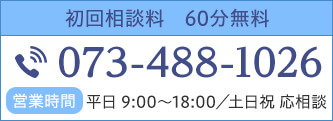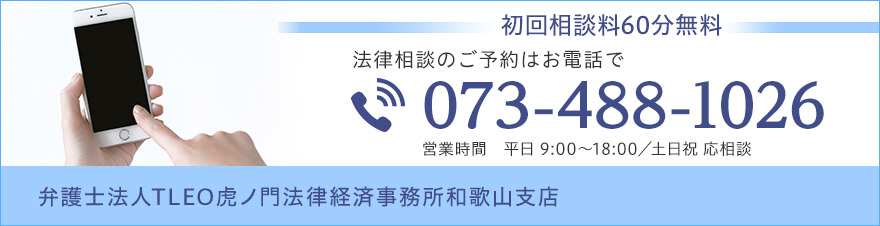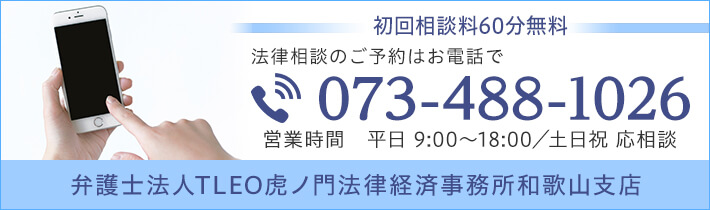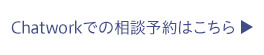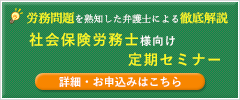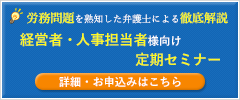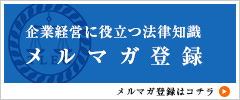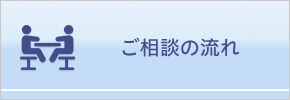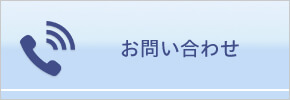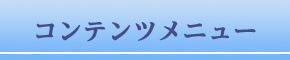2025年改正!育児介護休業法のポイント解説
はじめに
少子高齢化が進む日本において、仕事と育児・介護の両立支援は重要な課題となっています。このような状況を踏まえ、2025年に改正育児介護休業法の施行が予定されています。本改正では、育児や介護を行う労働者の働き方の柔軟化や、事業主による両立支援体制の整備が一層強化されることになります。今回は、2025年4月1日と10月1日の2段階で施行される改正内容について、企業の経営者の皆様が押さえるべきポイントを解説します。
改正の背景と目的
本改正は、少子高齢化が進行する日本社会において、働く親や介護を担う労働者の負担軽減を目的としています。従来の制度では、育児や介護に関する制度が限定的であったため、特に中小企業においては労働環境の整備が十分に進んでいませんでした。そこで、政府は制度の拡充と企業への対応義務の強化を図ることで、労働者が安心して長期にわたって働ける環境を整備し、ひいては企業の生産性向上や持続可能な経営に寄与することを狙っています。また、社会全体で育児や介護に対する理解を深めるとともに、働く環境の改善を促す狙いも含まれており、今回の改正は企業経営にとっても大きな転換点となります。
2025年4月1日施行の改正ポイント
子の看護等休暇制度の拡充
子の看護休暇等制度が大幅に拡充されます。従来は子どもの病気や怪我の看護、予防接種・健康診断に限定されていた取得事由が、感染症に伴う学級閉鎖や入園(入学)式・卒園式などの学校行事への参加まで拡大されます。また、対象となる子どもの年齢も、小学校就学前から小学校3年生修了まで引き上げられます。さらに、これまで対象外だった勤続6ヶ月未満の労働者も取得可能となり、より多くの労働者が制度を利用できるようになります。なお、週の所定労働時間が2日以下の労働者についてはこれまで通り、除外できる労働者となっています。
残業免除の対象範囲の拡大
現行法では、3歳未満の子を養育する労働者のみが対象となっていた残業免除制度ですが、改正後は小学校就学前の子を養育する労働者まで対象が拡大されます(改正法第16条の8)。これにより、保育園・幼稚園に通う子どもを持つ労働者も、より柔軟な働き方を選択できるようになります。なお、事業主は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、原則としてこの申出を拒むことができません。
3歳未満の子を育てる労働者のテレワーク選択の努力義務化
3歳未満の子を養育する労働者が育児休業を取得していない場合、事業主には在宅勤務等のテレワークを可能にする措置を講じる努力義務が課されます。罰則規定はありませんが、事業主には積極的な対応が求められます。なお、テレワーク導入にあたっては、業務内容の見直しや情報セキュリティの確保など、適切な労務管理体制の整備が重要となります。
介護のためのテレワーク選択の努力義務化
要介護状態にある家族を介護する労働者についても、事業主は在宅勤務等のテレワークを可能にする措置を講じる努力義務が課されます(改正法第24条第4項)。これは3歳未満の子を育てる労働者に対する規定と同様の対応が求められるもので、働く場所の柔軟性を高めることで、介護と仕事の両立を支援する狙いがあります。
テレワークの導入により、通勤時間の削減や急な介護ニーズへの対応が可能となり、介護離職のリスク軽減につながることが期待されます。また、オフィスワークとテレワークを組み合わせることで、介護する家族の状況に応じた柔軟な働き方の実現も可能となります。
事業主には、介護を行う労働者のニーズを把握し、業務内容や労働時間の管理方法、情報セキュリティ対策など、適切なテレワーク環境の整備が求められます。なお、この措置は努力義務であり罰則規定はありませんが、人材確保や従業員の定着率向上の観点からも、積極的な取り組みが推奨されます。
育児休業取得状況の公表義務の拡大
育児休業の取得状況の公表義務について、現行の従業員1,000人超の企業から、300人超の企業まで対象が拡大されます(改正法第22条の2)。この変更により、中堅企業においても育児休業の取得促進に向けた取り組みが加速することが期待されます。公表する情報には、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」が求められます。公表方法について、厚生労働省は「両立支援のひろば」というウェブサイトでの公表を推奨しています。
この改正により、中堅企業においても育児休業の取得促進に向けた取り組みが加速することが期待されます。また、この情報は求職者が企業選択の際の判断材料として活用することが想定されています。なお、女性の育児休業取得率や育児休業平均取得日数などの公表は任意となっています。この改正は、特に男性の育児休業取得率の向上を目指しており、労働者がより多様なライフスタイルに対応できる環境整備につながることが期待されています。
介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
子の看護等休暇と同じく、介護休暇でも、これまで対象外だった勤続6ヶ月未満の労働者も取得可能となりました。
この改正により、介護に直面した労働者は、勤続年数に関係なく必要な時に休暇を取得できるようになります。特に、中途採用者や新規事業の立ち上げに伴う採用者など、入社後間もない労働者であっても、家族の介護が必要となった場合には柔軟に対応できるようになります。なお、介護休暇は要介護状態にある対象家族が1人であれば年間5日まで、2人以上であれば年間10日まで取得することができ、この日数は勤続期間に関わらず付与されることになります。この制度の拡充により、介護離職の防止と、より働きやすい職場環境の整備が期待されます。なお、週の所定労働時間が2日以下の労働者については子の看護等休暇と同じく、除外できる労働者となっています。
介護離職防止のための新たな措置
介護離職防止のための措置が強化されます。事業主には、労働者が家族の介護に直面した際の個別周知・意向確認の義務、40歳到達時の介護支援制度の情報提供義務、そして介護休業の円滑な取得のための体制整備が求められます。具体的には、相談窓口の設置や介護に関する研修の実施など、計画的な取り組みが必要となります。
2025年10月1日施行の改正ポイント
柔軟な働き方を実現するための措置
3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置を2つ以上講じることが義務付けられます。
具体的な選択肢として、
- 始業時刻等の変更(フレックスタイム制、時差出勤制度)
- 月10日以上のテレワーク
- 保育施設の設置運営等(ベビーシッターの手配費用負担なども含む)
- 年10日以上の養育両立支援休暇の付与
- 短時間勤務
があります。
また、これらの措置について個別の周知と意向確認も必要となり、申出を理由とした不利益取扱いは禁止されます。
妊娠・出産に関する意向聴取と配慮の義務化
労働者からの妊娠・出産の申出に対して、事業主には仕事と育児の両立に関する意向聴取と、その意向への配慮が義務付けられます。これは、妊娠・出産後のキャリアプランを労働者と事業主が早期に共有し、計画的な両立支援を実現するための制度です。聴取した意向を理由とした不利益取扱いは禁止されており、適切な対応が求められます。
企業に求められる対応
就業規則等の社内規程の見直し
法改正に伴い、就業規則や育児・介護休業規程の改定が必要となります。特に、残業免除制度の対象拡大や看護休暇の取得要件の変更、新たな両立支援措置などについて、規定を設けることが重要です。また、改定した規程は労働基準監督署への届出が必要となります。
社内体制の整備と従業員への周知
新制度を円滑に運用するためには、人事部門を中心とした体制整備が不可欠です。具体的には、制度利用の申請手続きの整備、相談窓口の設置、管理職への研修実施などが必要となります。また、全従業員に対して新制度の内容を分かりやすく周知し、利用を促進する取り組みも重要です。
人員配置と業務分担の検討
育児・介護関連の制度利用者の増加に備え、業務の効率化や人員配置の見直しを検討する必要があります。特に、残業免除や看護休暇の対象拡大により、突発的な業務の発生に備えた体制づくりが重要となります。また、テレワークの導入・拡大に向けて、業務の切り分けやICTツールの活用など、新しい働き方に対応した業務設計も求められます。
まとめ
2025年の育児介護休業法改正により、育児や介護を行う労働者の支援策が大幅に強化されます。残業免除の対象が小学校就学前の子まで拡大され、看護休暇の取得要件も緩和されます。また、テレワークの選択や働き方の柔軟化など、従業員のニーズに応じた多様な働き方の選択肢も広がります。一方で、事業主には新たな義務や努力義務が課され、特に300人超の企業では育児休業取得状況の公表が義務化されます。このような法改正への対応には、弁護士等の専門家のアドバイスを受けながら、計画的に準備を進めることが重要です。法改正対応や就業規則の見直し、社内体制の整備などでお困りの方は、初回相談料は無料になっておりますのでお気軽に当事務所までご相談ください。