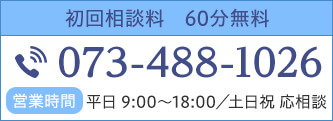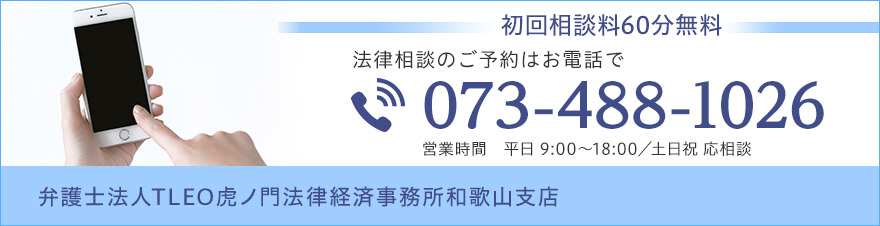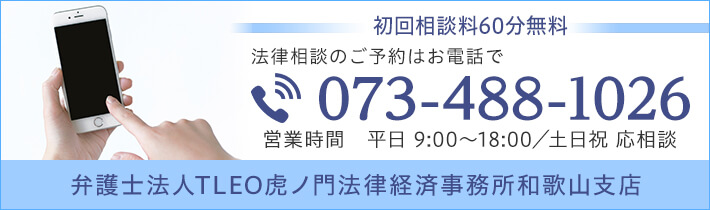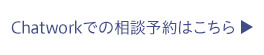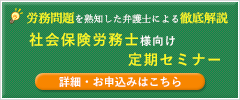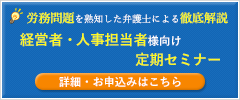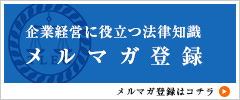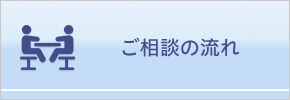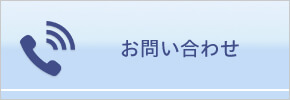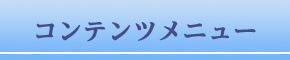企業がとるべきパワハラ対応策とは|注意すべきポイントを弁護士が解説
パワーハラスメント(以下「パワハラ」と略します。)の対応を誤ると、企業の信頼性が損なわれ、場合によっては訴訟にまで発展してしまいます。特に近年では、パワハラに対する社会的関心が高まっており、企業側の適切な対応が強く求められています。しかし、パワハラ発覚時は主観的な判断で処分を決定するのではなく、順序立てた対応方法に基づき、客観的な立場から調査や認定を行わなければなりません。また、パワハラを発生させないための予防策を講じることで、安心できる職場環境の構築に努めることも重要です。
本記事では、社内で発生したパワハラに対して、企業がとるべき対応策や予防策について解説します。さらに、パワハラの定義や具体例、リスクについても触れていきますので、経営者の皆様のお役に立てれば幸いです。
パワハラ(パワーハラスメント)とは?
パワハラとは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものと定義されています。
このパワハラの定義は、令和元年に、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(いわゆる「パワハラ防止法」と呼ばれるものですが、以下「労働施策総合推進法」と略します。)が改正されて明確にされたものです。
労働施策総合推進法第30条の2第1項においては、パワハラの定義①②及び③のような事態が生じないよう、パワハラ防止のために雇用管理上必要な措置を講じる義務を事業主に課すことが定められています。
また、労働施策総合推進法第30条の2第3項に基づいて定められた、厚生労働大臣による「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(略称:労働施策推進指針)では、パワハラの定義①②及び③の内容を深堀りした説明がされています。
具体的には、①「優越的な関係を背景とした」言動とは、当該事業主の業務を遂行するに当たって、当該言動を受ける労働者が当該言動の行為者とされる者に対して抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行われるもの、②「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動とは、社会通念に照らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、又はその態様が相当でないもの、③「労働者の就業環境が害される」とは、当該言動により労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることとされています。
会社経営者の皆さんが、これら法律上の定義やその意味を暗記する必要まではないかもしれません。しかしながら、大きな社会の変革の中で醸成され、結果として構築されたルールは考え方の出発点になるものですので,法律に定められたパワハラの定義①②及び③を念頭に置いた職場環境作りや万が一のときの訴訟対応が必要となることは心に留め置いていただければと思います。
パワハラ行為の具体例
パワハラの形態には様々なものがありますが、その具体例をいくつか紹介します。これらの事例を知ることで、自社の職場環境を見直す際の参考にしていただければ幸いです。
侮辱する言葉を発すること
仕事中に、相手を侮辱する言葉をかけることは精神的な攻撃として、原則として、パワハラに該当します。具体例としては、従業員に対し、「馬鹿野郎」「給料泥棒」等と発言するといったことが挙げられます。このような侮辱的な言葉を他の従業員のいる場で行うことはさらに悪質なパワハラと認定される可能性が高いといえます。
脅迫的な言動
「ぶっ殺すぞ」等、相手を脅迫する言葉をかけることも、同じく精神的な攻撃として、原則としてパワハラに該当します。また、壁やドア、机をたたいたりして大きな音を出して相手を威迫する行為も、パワハラに該当することになります。そのため、感情的になりやすい方は特に注意が必要です。
物理的な暴行
仕事中に上司が部下を殴ったりすることも身体的な攻撃として、パワハラ行為です。なお、身体的な攻撃については、いかなる理由があっても、「業務上必要かつ相当な範囲」に含まれることはありません。このような行為は刑事上の暴行罪に該当する可能性もあるため、絶対に避けるべきです。
職場での地位を利用した強要
上司が部下に対し、職場上の優越的な地位を利用して、業務とは関係のない私用を命じたり、遂行不可能な職務を強要することも、精神的な攻撃、過大な要求、個の侵害として、パワハラに該当する可能性があります。このような行為は、業務の効率性を著しく低下させるだけでなく、従業員の信頼も損なうことになります。
業務と関係のない嫌がらせ
上司が部下に対して業務に関する命令を発することは、上司に与えられた適法な権限ですから、原則としてパワハラに該当することはありません。しかしながら、業務と関係のない部下に対する嫌がらせ等の不当な目的に基づく業務命令は、精神的な攻撃、過大な要求として、パワハラに該当する可能性があります。
以上、パワハラの一例を紹介しましたが、パワハラの該当性はケースバイケースですので、具体的個別的な判断が必要となります。
ただし、ここで注意していただきたいのは、労働施策総合推進法上でいう「パワハラ」に該当したからといって、即座に「違法なパワハラ」として、損害賠償義務が認められる、という帰結にはならない、ということです。どういうことかというと、被害者とされる従業員が、パワハラ行為を理由とする損害賠償請求訴訟を提起する場合、労働施策総合推進法ではなく、民法第709条の不法行為が根拠になります。そのため、労働施策総合推進法上のパワハラに該当したとしても、民法上、違法とまではいえない、ということもあり得えるということです。
そのため、一口にパワハラと言っても、「管理職として不適切な行為」「懲戒処分の対象となる行為」「不法行為となる行為」のように段階があり、「不適切かもしれないが違法とまではいえない」という主張で、労働者側の損害賠償請求を棄却された、という裁判例もしばしば見受けられます。
もっとも、労働施策総合推進法上のパワハラに該当するような行為であれば、裁判上も、「違法」な行為と認定される可能性は高いので、会社としては、そのような行為が発生しないように、上記の定義をきちんと念頭において経営を行っていただければと思います。
企業がパワハラ対応策を講じるべき理由
パワハラへの対応は企業の義務
労働施策総合推進法によって、企業がパワハラ対策を行うことが義務付けられています。企業側は、従業員からパワハラの相談があった場合、必要な措置を講じなければなりません。さらに、パワハラの相談を行ったことを理由に、その従業員等に不利益な扱いをすることも禁止されています。パワハラが発生した場合、企業側には速やかな対応が求められます。パワハラ対策は世間の風潮に合わせて行うものではなく、法律上の義務であることを理解しておくことが重要です。
パワハラが企業に与える影響
パワハラは、被害者の仕事に対する意欲や生産性が低下するだけに留まらず、従業員の休職や退職といった職場を離れる事態を招き、これは周囲の従業員の士気を下げることにも繋がります。このような風潮が生まれてしまうと、人材不足などの問題も発生してしまいます。また、場合によっては企業の安全配慮義務違反を問われ、損害賠償請求をされる事態に発展することもあり、健全な企業運営を脅かす原因となります。パワハラは、被害を受ける従業員本人だけの問題ではなく、企業全体にとっても重大な問題であることを認識しなければなりません。
一方で、厚生労働省の『職場のハラスメントに関する実態調査について(令和5年度調査)』によると、ハラスメントの予防・解決のための取組を進めたことによる副次的効果として、「職場のコミュニケーションが活性化する/風通しが良くなる」「会社への信頼感が高まる」「休職者・離職者が減少する」「メンタルヘルス不調者が減少する」「従業員の仕事への意欲が高まる」等が挙げられており、きちんとパワハラ対策を行うことで企業へのプラスの影響も発生させることができます。
会社にとってのパワハラで訴えられるリスクとは?
パワハラの被害者に対し、企業が責任を負う根拠として、使用者責任としての損害賠償請求があります。使用者責任とは、従業員が業務中に損害を発生させた場合、従業員を雇用している使用者たる企業も損害賠償責任を負うというものです(民法第715条第1項)。
また、企業は、労働契約を締結している従業員に対して、労働契約の付随義務として職場環境配慮義務(安全配慮義務とも呼ばれます。)も負うとされ、この義務を怠ったとして債務不履行に基づく損害賠償責任を問われることも考えられます。
損害賠償の内容としては、パワハラを受けたことに伴う精神的苦痛いわゆる慰謝料のほか、パワハラによって体調等を崩したことに伴う治療費、消極損害として休職を余儀なくされたことに伴う休業損害、稼働能力減退にともなう将来にわたる逸失利益等が考えられます。
パワハラで訴えられたことに伴う企業のリスクは金銭的な損害に限られません。場合によっては、事態の収拾が見込めなくなり、企業の不祥事としてマスコミによって報道がなされたり、ネット上に企業の対応のまずさが流され拡散する等の危険にも晒されることになってしまいます。
繰り返しになりますが、企業はパワハラ防止の措置を講じることが法律上義務づけられています(労働施策総合推進法第30条の2第1項)。会社経営者の皆さんは、パワハラの問題が生じた場合に企業の責任が常に問われること、訴えられた場合のリスクが極めて高いことを強く認識していただき、これらのリスクを回避するための事前・事後の対策を恒常的に構築していかなければならない責務があることを意識しなければなりません。
パワハラ発生時に企業がとるべき対応手順
事実関係を調査する
従業員からパワハラの相談があった場合、まずは事実関係を調べることが重要です。被害者だけでなく、行為者や周囲の関係者も含めて広くヒアリングを行います。また、パワハラの事実を証明するメールや録音などの証拠の有無も確認しましょう。可能な限り、客観的な事実判定を行えるように調査を進めましょう。
企業内におけるパワハラを早期に解決するためには、企業内における相談窓口を設けておくことが大切です。相談窓口は、企業内の人事部・総務部・管理部、あるいは、外部の専門家を相談窓口として設定することもあります。
公平な事実調査のためには、加害者及び被害者、双方からしっかりした聴き取り(ヒアリング)をすることはもちろんですが、聴き取りをする人選にも配慮が必要です。もし、聴き取りをする人物が、加害者か被害者かどちらかに近しい立場にあるとすれば、到底公平な調査を実施することは難しく、解決は遠のいてしまうでしょう。また、パワハラの中でも、セクハラの要素が混じっているようなものであれば、聞取りをする者の性別にも配慮が必要かも知れません。
ヒアリングの方法
事実関係の調査においては、公平さが保たれるように配慮する必要があります。また、加害者や被害者とは利害関係のない第三者への聴き取りも事実関係の確認にあたっては重要になります。
聴き取りの順序は、まずは被害申告内容の確認も含めて、被害者から行うのが一般的です。ヒアリングの際は、5W1Hを意識して、具体的な中身(「暴言を吐かれた」→「『お前みたいなやつは死んじまえ』と言われた」)を特定するようにしてください。なお、被害者が精神的にダメージを受けているような場合は、カウンセラーを同席させるといった対応も検討する必要があるかもしれません。
被害者からのヒアリングが終了したら、加害者からのヒアリングに入ります。ただし、事案によっては、加害者からの二次被害の恐れもあることがあります。そのような場合は、当該加害者には、調査期間中は自宅待機を命じて、出勤させない、といった毅然とした対応をすることも必要です。なお、自宅待機は懲戒処分ではないので、原則として、賃金は全額支給してください。時と場合によっては、そこまでしても、会社は従業員を守らなければならない場面があります。
なお、名古屋地判平成3年7月22日は、「このような場合の自宅謹慎は、それ自体として懲戒的性質を有するものではなく、当面の職場秩序維持の観点から執られる一種の職務命令とみるべきものであるから、使用者は当然にその間の賃金支払い義務を免れるものではない。そして、使用者が右支払義務を免れるためには、当該労働者を就労させないことにつき、不正行為の再発、証拠湮滅のおそれなどの緊急かつ合理的な理由が存するか又はこれを実質的な出勤停止処分に転化させる懲戒規定上の根拠が存在することを要すると解すべきであり、単なる労使慣行あるいは組合との間の口頭了解の存在では足りないと解すべきである。」と判示しており、一定の場合には、自宅待機期間中の賃金を支払わなくても良い場合があることを認めていますが、このような場合に該当することは稀であると思われます。
企業の側においては、聴き取った内容を議事録に残すかたちで書面化するのがよいでしょう。ヒアリング後は、聴き取った内容を書面化し、事実関係を時系列順に整理する等して、関係者間の言い分の食い違い(争点)等を抽出する等して、最終的に、会社として、事実関係の有無を判断することになります。
パワハラの有無を判定する
調査で得た事実内容をもとに、パワハラがあったと認められるかどうかを判断します。事実認定は、客観的な視点から見れていることが重要です。自社内での判断では意見の偏りがあると感じる場合は、弁護士などから客観的な意見を聞くことをおすすめします。認定した事実関係は、調査報告書にまとめて、関係者に通知します。この調査報告書は訴訟になった際の証拠になるため、調査方法に不備が無いことや客観的な判断がなされているかが重要となります。
事実関係がない(誤解である場合など)は、そのような結果を本人に説明するとともに、このような誤解が生まれないようにするための措置を検討します(その措置についても、本人に説明しておくと良いです。)。ただし、この時、本人が納得していない様子であれば、加害者とされる従業員に対し、「今後、被害者から訴訟等を起こされたり、弁護士から内容証明郵便が届いたような場合は、必ず会社に報告して、自分一人の判断で対応しないこと」を約束させておくのが良いでしょう。
被害者への配慮措置を講じる
調査結果を被害者・行為者の本人たちに通知するとともに、被害者への配慮措置を迅速に行います。具体的には、事案の内容を考慮した上での行為者との関係改善に向けての援助、行為者と引き離すための配置転換等を行います。また、被害者にメンタルヘルス不調が見られる場合は、管理監督者または事業場内産業保護スタッフ等による相談対応等を行います。
会社の結論如何にかかわらず、被害者に対しては、経過や結果ついて、報告・説明することを忘れないでください。適切な報告や説明を通じて、被害者の信頼を得ることが、さらなる問題発生を防ぐ上で非常に重要です。
行為者への処分を決定する
事実関係があると判断した場合は、本人に中間報告を行いつつ、加害者に対する懲戒処分をするかどうかの検討を行います。そして、懲戒処分をしたかどうか、したとしてどのような処分になったのかを、被害者に報告します。
パワハラの事実が認定された場合は、行為者への処分を検討する必要があります。パワハラの内容や行為者の反省度合い、会社の就業規則などを考慮しながら適切な処分を検討しましょう。懲戒処分を行うことで、行為者本人に強い制裁を与えることができるだけでなく、他の従業員に対して企業側の姿勢を示す効果もあります。しかし、安易に降格や懲戒解雇といった重い懲戒処分を下してはいけません。客観的・合理的に妥当な処分でなければ裁判で無効と判断される可能性があるため、注意が必要です。
その他にも、被害者への配慮措置と合わせて、配置転換や被害者への謝罪等の措置も行いましょう。このような調査・事実認定にあたっては、専門的な知識や経験が必要となるケースもありますので、弁護士等の外部の専門家にアドバイスを求めたり、依頼をすることが適切です。
企業法務に強い弁護士は、法的な観点からいかなる事実についての聴き取りが重要かを熟知していますから、不十分だったヒアリングをやり直し、重要な事実や虚偽内容を選別することで、実態解明に大きく資する役割を果たすことができます。パワハラ発生における事実確認・事実認定には高度な専門的な知識や経験が必要であることをふまえ、早期の段階で企業法務に強い弁護士に依頼することも検討してみてください。
パワハラを予防するために必要な対応
社内規定を整備する
パワハラを予防するためには、あらかじめ社内におけるルールを明確にしておかなければなりません。パワハラに関する社内規定を整備し、企業としての対処方針を明示しましょう。特に、パワハラ行為者に対する懲戒処分など、罰則に関する内容を示すことが重要です。罰則の規程が明示されていることでパワハラの抑止効果があるだけでなく、従業員に安心感を与えることができます。
労働施策総合推進法は、企業に対してパワハラ防止措置を講じることを義務付けていますが、これとは別に、事業主に対してもパワハラ問題に関する責務を定めています。労働施策総合推進法第30条の3第2項は「事業主は、優越的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講じる前項の措置に協力するように努めなければならない。」と定めています。
この条文にいう「優越的言動問題」とは、先のパワハラの定義①を踏まえたものであり、優越的な関係を背景とした言動によって生じる様々な問題のことを意味しています。具体的には、労働者における意欲の低下、健康状態の悪化、また、職場における職場環境の悪化、生産性の悪化等を指します。
相談窓口を設置する
パワハラは、早期に発見して被害拡大を防止することが重要です。ハラスメント等を対象とする相談窓口を設置して、従業員がハラスメントに関する悩みについて話しやすい環境を整えましょう。社内に窓口を設けるだけでは、被害者が人事評価や情報漏洩を懸念して相談をためらう可能性があります。そのため、相談窓口は弁護士等の社外にも設置することをおすすめします。
これらパワハラ問題に対する労働者の関心と理解を深めるために、会社経営者の皆さんには、職場内における言動に対する注意を喚起したり、研修を行う等の必要な配慮を講じる努力義務が求められているのです。
また、労働施策総合推進法第30条の3第3項は「事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)は、自らも、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。」と定めています。優越的言動に対する対処は、労働者だけではなく、企業そのものや役員に対しても関心と理解を深めてもらうことが必要であり、事業主が啓発活動に努めることがうたわれています。
従業員の理解を深める
パワハラが発生する要因の一つに、従業員が当該行為をパワハラだと認識できていないことがあるため、従業員のハラスメントへの理解を深める必要があります。具体的には、一般従業員・管理職それぞれを対象としてパワハラに関する研修を行うことが挙げられます。パワハラの定義や企業としての対処方針、相談窓口などについて説明をすることで、発生の抑制・早期の発見に繋がります。職場内の意識向上を図ることが重要です。
また、研修の講師として、弁護士を起用することも効果的です。弁護士であれば最新の法令や判例を踏まえた具体的な解説等ができるため、従業員のパワハラへの理解を深めるだけでなく、企業のコンプライアンス体制強化にも繋がります。
これら事業主の責務は、努力義務として定められているにすぎませんが、事業主のパワハラ防止に向けた広報活動や啓発活動は、企業におけるパワハラ防止の措置を講じる法律上の義務(労働施策総合推進法第30条の2第1項)に直結するものです。会社経営者の皆さんは、パワハラ問題に関する関心と理解を企業全体で共有することがパワハラ防止の第一歩であることを念頭に、必要な広報活動や啓発活動に邁進していただくよう心がけていただければと思います。
定期的に実態調査を行う
企業側が積極的に実態の把握に努めることも重要です。社内でパワハラが発生していないか、または発展しそうな状況の有無を定期的に調べましょう。手段としては匿名アンケートが特に有効です。ハラスメントを受けているかどうかという直接的な質問はもちろん、ハラスメントを見たことがあるかという間接的な情報も集めることで、より具体的に状況を把握できます。被害者の訴えによって発覚する事例は氷山の一角に過ぎないという可能性もあるため、企業側から積極的に調査する姿勢が重要です。このような定期的な実態調査は、パワハラの早期発見・早期対応に繋がるだけでなく、従業員に対して「会社はパワハラ問題を重視している」というメッセージを伝える効果もあります。したがって、定期的な実態調査を通じて、パワハラのない健全な職場環境づくりを目指しましょう。
パワハラ対応で注意すべきこと
パワハラの対応は迅速に行う
パワハラの相談があった場合は、速やかな対応を心がけましょう。相談を放置したり、パワハラを軽視して被害者に対して雑な対応をしたりすることは絶対にしてはいけません。パワハラに関する訴訟では必ずと言っていいほど「会社に相談したが対応してもらえなかった」という主張がでてきます。そのため、相談があってから迅速に対応し、その履歴を残すことが非常に重要です。なぜなら、従業員からの会社への信頼感の向上に繋がるだけでなく、万が一、訴訟に発展した際も企業として取るべき措置を講じたことを主張・立証することができるからです。特に、パワハラの初期対応を適切にしておかないと、被害者の不満が高まり、加害者もあまり重大に捉えないという悪循環に陥りかねません。したがって、パワハラの相談があった場合は、企業としての責任を果たすためにも、迅速かつ誠実な対応を心がけましょう。
ヒアリングは広範囲に行う
事実確認の調査時に行うヒアリングは、できる限り広範囲に行うことが重要です。被害者の意見を真摯に聞くことは大切である一方、被害者の主張が事実と異なる可能性も考えられます。そのため、行為者側の意見や、周囲の第三者たちの意見も必ず聞くようにしましょう。事実認定は客観的に納得できる結論であることが重要であるため、中立の立場で事実確認を進める姿勢が求められます。また、ヒアリングをする際は、「5W1H」を意識して、具体的な内容を特定するようにしてください。例えば、「暴言を吐かれた」という曖昧な証言ではなく、「『お前みたいなやつは死んじまえ』と言われた」というように具体的な内容を確認することが重要です。さらに、被害者が精神的にダメージを受けているような場合は、カウンセラーを同席させるといった配慮も必要となるでしょう。
関係者のプライバシーへの配慮を欠かさない
パワハラ対応を進める過程では、関係者のプライバシーへの配慮が欠かせません。ヒアリング資料には個人を特定できる情報が載っているため、たとえ裁判であっても資料の公開には細心の注意を払いましょう。特に、聴取した情報を行為者に見せるといった行為は思わぬ二次災害を招きかねないため、慎重な対応が必要です。また、資料を誰かに公開する場合は、必ず本人たちの許可を得ることが重要です。このように、関係者のプライバシー保護に配慮しつつ、公平かつ透明性のある調査を進めることで、企業としての信頼性を維持することができます。したがって、パワハラ対応においては、関係者のプライバシー保護と適切な情報管理を徹底しましょう。
まとめ|パワハラ対応は弁護士に相談を
パワハラの相談を受けた場合、事実の調査と認定を中立的に行い、被害者へのフォローや行為者への処分を迅速に行う必要があります。そして、社内規定の整備や相談窓口の設置などを進めることで企業側の対応姿勢を示し、パワハラの予防に努めることが重要です。しかしながら、パワハラの対応は高度な専門知識が必要となるケースも多く、自社内の都合に影響されず客観的な判断を行うことが困難な場合もあります。そのため、弁護士などの専門家に第三者視点の意見やアドバイスを求めることをおすすめします。弁護士は、法的な観点からいかなる事実についての聴き取りが重要かを熟知しており、不十分だったヒアリングをやり直し、重要な事実や虚偽内容を選別することで、実態解明に大きく資する役割を果たすことができます。虎ノ門法律経済事務所和歌山支店では、企業人事、労務問題に関する経験が豊富な弁護士が、予防策の検討から訴訟対応まで徹底的にサポートいたします。パワハラ対応にお悩みの際は、ぜひご相談ください。