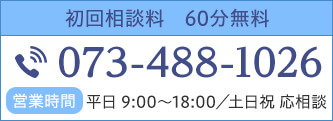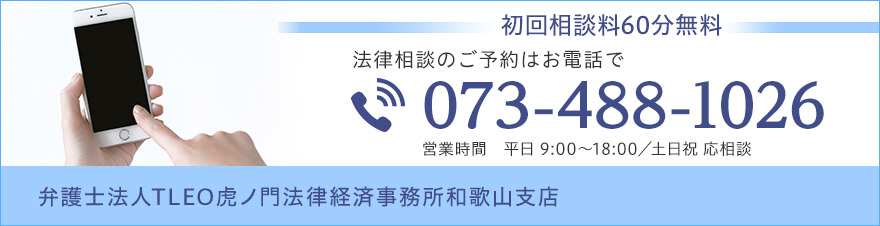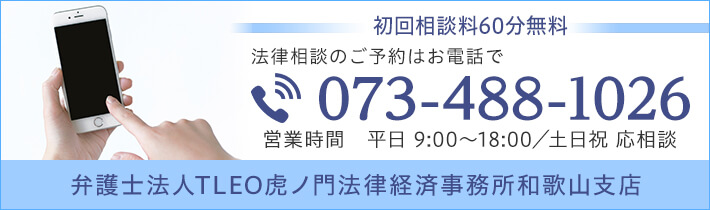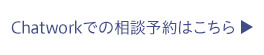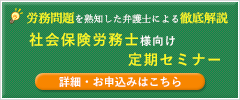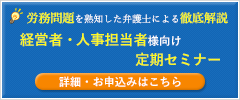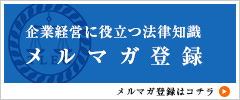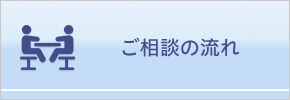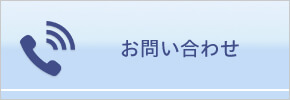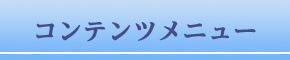工事代金の未払いが発生!回収の流れと注意点を解説
工事を請け負ったにも関わらず工事代金が未払いのまま放置される事態は、建設業・建築業界では元請け・下請けの構造が生まれるため、発生しやすいトラブルです。下請けという立場上、元請会社へ支払を強く求めることができず、悩まれている方も多いのではないでしょうか。しかし、工事代金の未払を放置すると、自社の資金繰りが悪化するなど多くのリスクを生みかねません。
そこで本記事では、工事代金の未払いが発生する要因や未払工事代金の回収方法等を解説します。
工事代金の未払いが発生する要因
工事代金の未払いが発生した際の対応として、まずは未払いの要因を確認する必要があります。要因によって対応が大きく異なるからです。工事代金未払いの原因となりやすいケースは次のとおりです。
発注者側に問題があるケース
工事代金未払いが発生する第1の要因として、発注者側が意図的に支払いを行っていない、発注者側にトラブルが発生した、というケースが考えられます。具体的には以下のような例が挙げられます。
・発注者側の資金繰りが悪化した
・工事の仕上がりに不満がある
・追加工事分の費用の支払に不服がある
特に、発注者側の経営状況が悪化して支払いができなくなっている場合、倒産などで代金を回収できなくなる可能性もあるため、迅速な確認と対応が重要となります。
契約書に問題があるケース
第2の要因として、請負契約を締結したにもかかわらず、契約書の内容が不十分であるがために想定外に支払いが滞ってしまう事態が考えられます。例えば、代金の額、支払時期や回数などについて定めていないケースが挙げられます。小規模の工事であれば工事代金を完成後に引き渡しと同時に一括払いされる場合もあります。しかし、工期が長く請負金額も大きい工事の場合は、以下のように複数回の支払いについて定めることで対策することが可能です。
・工事開始時(契約金・着手金・前払い金)
・工事期間中の出来高払い(中間払い)
・完成後・引き渡し時
また、契約書に金額の明確な記載がないことによって、そもそもの支払代金額の認識に当事者間で総意があり、争いになる、ということもよく見られます。
他にも、工期途中で材料などの価格高騰があった際はどちらが負担するのかなど、様々なリスクを想定して契約書を締結しなければなりません。契約書の内容が不十分だとトラブル発生時に有利な解決ができなくなるため、契約書の作成はもちろんのこと、契約締結前に入念なチェックが必要です。見積書や請求書などの重要書類も必ず保管するようにしましょう。
これらの資料がないと、弁護士が代金回収案件としてお受けすることも難しい、ということになりかねません。
完成した建物を先に引き渡したケース
下請け業者は、元請け業者に対して弱い立場にあります。そのため、元請け業者の要望があると、完成した建物を代金が支払われるよりも先に建物を引き渡してしまうケースが往々にしてあります。しかし、請負契約では、完成した目的物の引き渡しと同時に報酬の支払いが行われるように定められています(民法第633条)。
また、建物について商事留置権が成立するためには、建物の所有権が注文主に認められる必要があります。商法521条は「物」について留置権が成立するとしています。そのため、契約書上で「建物の所有権が発注元に帰属する」等の規定があれば、建物につき商事留置権が成立することになります。もっとも、代金が支払われるより前に建物を引き渡してしまえば、商事留置権は行使できなくなります。商事留置権という権利があることを念頭に置いた上で、物件の引き渡しは慎重に行いましょう。なお、建物の建っている土地については商事留置権を成立させない、という裁判例があります。その根拠としては、商事留置権は債権者が目的物を占有していることが要件であるところ、建物建築請負人には商事留置権成立のために必要な敷地の占有が認められない、というものです。
未払いの工事代金を回収する流れ
電話やメールでの催促
工事代金の未払いが発生した場合、まずは電話やメールで相手方に支払いを催促します。
単なる事務手続きのミスであればすぐに解決するでしょう。資金難が理由であれば、返済の計画を協議する必要があります。
まずは相手方に確認の一報を送ることが重要です。
内容証明郵便による催告
催促をしても払ってくれない場合は、弁護士に依頼して内容証明郵便を送付し、支払いを求めます。内容証明郵便であれば、催促をしたという事実を証拠として残すことが可能です。
書面には次の内容を記載しましょう。
・支払期限と金額
・支払先銀行口座
・未払いが続けば法的手段を取ること
・訴訟になれば遅延損害金や弁護士も併せて請求すること
弁護士名義で催告を送ることで、期限までの支払いをしなければ法的手段を取るという意思を明確に伝えることができ、直ぐに支払い対応をしてもらえることは非常に多いです。内容証明郵便による催告の中でも、弁護士名義にするかどうか、まで検討するようにしましょう。
支払督促
支払督促とは、裁判所から支払督促(督促状)を送ってもらう手続きです。いきなり通常の訴訟を起こすのではなく、まずは支払督促での解決を目指します。支払督促のメリットは、訴訟よりも手続きが簡単な上に費用が安いことが挙げられます。また、相手から異議申し立てがなく支払いもなければ、自動的に強制執行へと移れます。
訴訟手続き
裁判所に訴えを起こす前に相手方の資産に仮差押え手続を実施することが重要です。強制執行が可能になるまでに相手方が資産を移動させたり隠したりすることで、回収ができなくなるリスクを減らすことができるからです。
仮差押えが完了すれば、裁判所に未払いの工事代金支払いを求める訴訟を起こすという流れになります。請求金額が60万円以下であれば、少額訴訟を利用して時間や費用を押さえることも可能です。他にも民事調停や即決和解といった方法があるため、事案に応じて最適な方法を検討しましょう。
なお、相手が別の工事を請け負っており、その工事代金を仮差押えしたい、という場合もあるでしょう。単発的な請負工事についての請負代金債権であれば、債権の種類(請負代金債権であること)に加え、契約日、目的である仕事の種類及び内容(工事代金であれば、工事名、工事場所、工期等)、代金額、弁済期等を記載するなどして特定して、仮差押えを申し立てることになります。
もっとも、仮差押えをしたいと考えたとしても、相手の工事等の詳細を的確に把握することが困難である場合も多いと思われます。そのような場合に、具体的にどこまでの特定を要するかについては、事案に応じて裁判所と協議することが多いと思われます。
強制執行
裁判での勝訴や和解調書をもとに債務名義を得られると、相手の預金や不動産などを差し押さえて、工事代金を強制的に支払わせることができます。
未払いの工事代金を回収する際に知っておくべきこと
特定建設業者の立替払い制度
元請け業者が「特定建設業者」の許可を受けている場合、立替払い(建設業法第41条第3項)を利用して工事代金の請求をすることができます。特定建設業者とは、一般よりも代金が高額になる工事を下請契約で施工できる許可を得ている業者のことを指します。立替払い制度を利用する場合は、国土交通大臣または都道府県知事に、元請け業者(特定建設業者)に対して工事代金の立替え払いの勧告をするように求めます。指導や勧告に従わないと業務停止処分を受けることもあるため、が立替払いに応じることが期待できます。
工事代金請求の時効
工事代金の請求には時効があることに注意しなければなりません。現在の民法では、工事代金を請求できるのは支払期限から5年までです(民法第166条)。なお、仮に、2020年4月1日以前に締結された請負契約であれば、3年で消滅時効にかかります。これは、改正前の民法に、短期消滅時効という制度があったことによります。
以下のような対応をとらなければ、5年で代金請求権を失います。
・訴訟あるいは支払督促を起こす(民法第147条)
・発注者に支払義務を認める書面を書かせる(民法第152条)
・未払い工事代金の一部を払ってもらう(民法第152条)
時効の成立までに期間があまりない場合は更新・完成猶予の制度を使って時効を引き延ばすことが重要です。したがって、素早く措置をとることができる弁護士に依頼することをおすすめします。
契約書がない場合
契約書がない口約束のみの契約であっても、法律上は効力が生じるため、契約書が未締結で工事を行った場合も工事代金の支払いを請求することは可能です。しかし、訴訟で契約の有無が争われた場合、契約書が無ければ請負契約があったことを証明することが難しくなります。したがって、契約書を作成していなかった場合は、見積書・請求書・設計図など、契約があったことを確認できる資料を残すことが重要になります。紙媒体の証拠がない場合でも、メールなどの電磁的記録を駆使すれば契約の存在を立証できる可能性は上がります。
契約書が未締結でトラブルに発展してしまった場合は、できる限りの資料や相手方とのやり取りを記録したものを集めるようにしましょう。
工事代金の未払いでお困りなら当事務所まで
工事代金の未払いが発生した場合、まずは原因を確認した上で、相手方に直接催促することで代金回収を図ります。支払いに応じてくれなければ、催告を行ったうえで裁判所による法的な手続きに踏み切りましょう。特定建設業者の立替払い制度や時効制度を考慮しながら回収計画を進めることが重要です。迅速かつ正確に対応を行うためには、弁護士に専門的なアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所和歌山支店では、企業法務の経験が豊富な弁護士が徹底サポートいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。